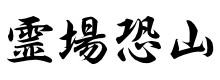1.恐山の歴史
恐山は、慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)様(日本天台宗・比叡山延暦寺第三世座主)によって、西暦862年(貞観4年)に開かれたとされています。
ただ、恐山の歴史的文書は、近世以前のものは戦乱・火災等でほとんどが失われ、資料として遡れるものは江戸時代までです。
様々な伝承などを総合すると、この地は当初、湯治場として地元の人々に発見されたと思われます。境内の温泉も歴史が古く、「薬湯」として参拝者に利用され、病気平癒など、恐山の現世利益信仰の一端を担ってきました。

八つの山に囲まれ、火山岩に覆われた地帯とカルデラ湖の風景は、独特の異界的雰囲気に満ち、9~10世紀ころには、主に天台密教系の修験者(民間の山岳修行者・山伏)が入山して、修行・布教活動を始めたと推定されています。
その後の恐山について確実な資料はなく不明だが、戦乱等で荒廃し、16世紀半ば、本坊円通寺開山・宏智聚覚(わんしじゅがく)和尚によって再興されました。以後、恐山は日本曹洞宗・円通寺が管理しています。
地蔵殿をはじめ、現在の主要な建築物は、現山主によって、最近30年間に新築されたものです。

2.恐山の信仰
恐山の本尊は、正面の本殿、地蔵殿にお祀りする延命地蔵菩薩です。釈迦牟尼の入滅後、地獄から天上までのあらゆる世界の人々の苦しみを救い、平安をもたらすとされています。観世音菩薩と並び、日本では最も親しまれています。
その他、恐山には釈迦牟尼如来、阿弥陀如来、薬師如来、観世音菩薩、不動明王と、様々な仏像が祀られており、信仰は特定の宗派の教義にとらわれていません。
現在の信仰は、地蔵殿にてご参拝の方々の日々の幸福を祈祷し、本堂で亡くなられた方々の供養を行うことを中心としています。
昭和30年代から、「イタコ」と呼ばれる女性霊媒師が集まるようになり、「口寄せ」という降霊術が境内で行われるようになりました。彼女たちは恐山に所属しているわけではなく、恐山も彼女たちを管理しているわけではありません。最盛期は30人を超える「イタコ」の上山がありましたが、現在は数人程度です。
※ 新聞、雑誌、テレビ、Web等による取材・撮影は事前に恐山の許可が必要です。