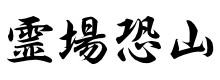入山料
大人1名
700円
団体(20名以上)
1人 600円
小学生
300円
幼児
無料
障害者手帳等携帯者及び
介助者1名まで
無料
ペットの入山
不可
参拝中のお願い
- 参拝順路から出ないで下さい。高温の火山ガスが噴出している場所がところどころにあり、危険です。
- 境内にある仏像・物品、植物・石等に触れたり、それらを持ち帰ったりしないで下さい。
- 他の参拝者の迷惑になる行為はしないで下さい。

1.太鼓橋・三途の川
山中の恐山街道を抜けると視界が開け、左手に宇曽利湖が見えます。その先にこの湖から流れ出る唯一の川があり、これを「三途の川」と言います。仏教では、この世(此岸)とあの世(彼岸)を分ける川とされています。この川に架かるのが太鼓橋です。死者はこの橋を渡って彼岸に行くわけです。

橋の渡口にある二体の像は奪衣婆と懸衣翁です。経典では、亡者が三途の川まで来ると、奪衣婆が亡者の衣服をはぎ取り、これを懸衣翁が木の枝に懸けて、そのしなり具合で生前の悪業の重さを計り、死後の行き先が決まると説かれています。

2.六地蔵
仏教では、この世界は地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六つに分かれ(六道)、それぞれに苦しむ衆生がいるとされます。その六つの世界で、大いなる慈悲によって衆生を救うのが、六地蔵です。

3.総受付
入山料を頂き、入山券と案内パンフレットをお渡しします。


4.総門・参道・石灯篭
土塀で仕切られた境内の正面が総門です。そこから本尊地蔵菩薩を安置する地蔵殿まで、一直線に参道が続きます。
参道左右の石灯篭は全部で43基あり、江戸時代末に、北前船を主とする海運業に関係する廻船問屋、商人、船主などから寄進されました。下北半島最高峰の釜臥山の神(釜臥山嶽大明神)は、恐山本堂の本尊、釈迦牟尼仏の化身とされ、航海する船舶の守護神であり、海上安全・航海無事を祈る人々の帰依を受けたのです。

5.山門
左右に阿形・吽形の仁王像が境内を守護し、楼上には曹洞宗大本山第78世貫首、宮崎奕保禅師様の御親筆による山号額を掲げています。楼上内には、釈迦牟尼仏の下で悟りを開かれた十六大阿羅漢・五百大阿羅漢などをお祀りしています。

6.寺務所
山門の右に位置します。恐山の運営と事務を司っています。御朱印の記帳、塔婆供養(ご先祖供養)・ご祈祷など、法要の受付をします。

7.本堂
山門の左です。曹洞宗寺院としての恐山菩提寺の本尊、釈迦牟尼仏をお祀りします。塔婆供養の法要は、この本堂(別名は菩提堂)で行います。
正面奥の左右の棚には、亡くなられた方々の遺影や、衣服などの想いでの品々が納められています。さらに堂内には故人の遺品や写真のほか、独身のまま亡くなった子供を来世で結婚させたいと望む家族が奉納した、花嫁・花婿人形が多く置かれている。
この建物は元々武術道場で、戦後に移築されたものです。境内の建物では古いものです。

8.宿坊「吉祥閣」
ご参拝で宿泊なさる方々の宿舎です。一般の旅館ではなく、参拝施設なので、朝のお務めへの参加等、いくつかの規則・作法を守っていただきます。
食事は精進料理で、肉・魚は一切出ません。また、大浴場の湯は境内の温泉と同じで、様々な効能があります。

9.境内の温泉
恐山は、霊場となる以前には、地元の人々が温泉を発見し、湯治場として知られるようになったと考えられています。
境内には4湯の温泉(古くは5湯)があり、それぞれに薬効があります。参道右側の薬師の湯は眼病、左側の冷えの湯(別名冷抜の湯)は神経痛やリュウマチ、同じく古滝の湯は胃腸病、宿坊裏の花染の湯(現在調整中で入浴できません)は肌によいとされます。
なお、花染の湯は混浴、その他の湯は日により男女を入れ替えます。

10.地蔵殿
参道正面が、霊場恐山の本尊延命地蔵菩薩像を奉安する地蔵殿です。ここでは主に祈祷の法要を行っています。
地蔵像は約2メートルで、開山慈覚大師の彫刻と言われます。僧侶の法衣や袈裟を着用した仏像は非常に珍しく、ほとんど例がありません。

伝説では、地蔵像は夜間に地蔵殿を出て、境内を歩き、未だ霊魂として彷徨っている人々を救済すると言い伝えられています。昔の法衣は裾が千切れたままで、それは救われたい人々がすがりつくからだと説かれていました。
地蔵菩薩の両側の童子像は、地蔵菩薩に使える子供の修行者で、善を勧め悪を斥けるとされています。

地蔵殿奥の開山堂には、正面に開山慈覚大師像を奉安しています。
右側の十一面観音像と左側の観音菩薩半跏思惟像は円空仏師の作(素朴な鉈彫りで仏像を制作した、日本では非常に人気の高い、江戸期の僧侶彫刻家)です。
大師像右隣りの特異な様式の仏頭と両手は、1883年の旧地蔵殿改築の際、土中より発見されました。
開山堂は常時公開しているわけではありませんので、ご注意ください。

11.薬師堂
地蔵殿の右にあるのが薬師堂です。病に苦しむ人々を救うとされる薬師如来をお祀りしています。常時公開しているわけではありませんので、ご注意ください。

12.奥の院・不動明王
地蔵殿の裏山に不動明王が祀られています。経典には、地蔵菩薩と不動明王は「二面不二」とされ、19世紀半ば(江戸時代後期)には信仰されていたと思われます。

13.「地獄めぐり」
地蔵殿の左から、古くから地獄に見立てられた、火山の噴石に覆われた岩場に入ります。右手上の巨大な岩は大王岩と呼ばれ、閻魔大王とされています。
参道の両脇には、ところどころに参拝者が草を結んで作った草の輪があります。賽の河原で子供を追いかける鬼の足を引っかけて転ばそうとする、来世で再びわが子と結ばれる、死者と深く縁を結ぶ、などの願いから始まった信仰と言われています。

14.大師堂
参道途中にも慈覚大師をお祀りする太子堂があります。太子堂周辺、さらに参道沿いの所々に立てられている風車は、亡くなった子供への供養として始まり、今は花の代わりとして、子供に限らず故人の供養に立てられています。

15.賽の河原
「地獄めぐり」の参道を下ると、左に平坦な土地が広がります。そこには無数の石積みが見られます。これは賽の河原の説話に基づいています。
説話によると、賽の河原は、この世とあの世を分ける「三途の川」のほとりにあります。ここは、親を遺して亡くなった子供たちが集まり、石を積んで塔を造り、それを仏に供養して、得た功徳を親に回向して、現世でできなかった親孝行をする、とされています。
ところが、石を積んで塔ができかかると、鬼が現れてそれを壊してしまいます。すると、子供たちは再び小石を拾っては1つずつ積み上げ、塔を作り始めるのです。これを繰り返す子供たちを救うのが、賽の河原の地蔵菩薩なのです。
この説話にちなみ、報われない努力のことを、ことわざで「賽の河原の石積み」と言います。
現在では子供に限らず、亡くなられた大切な人の追慕と供養のために、参拝の方々が石を積まれていきます。

16.八角堂
内正面の地蔵菩薩像は、賽の河原の本尊とされ、実際にはこの像が恐山最古のものであるとする説があります。
堂内に奉納されているのは、本堂同様にすべて遺品で、主に衣服、履物、写真ですが、玩具、時計、眼鏡などもあり、亡くなった家族を偲ぶものが多く奉納されています。
この八角堂裏の雑木林など、境内のあちこちには、多くのタオルや手拭、草鞋などが結び付けられています。これは、死者が死後の世界と恐山の間を往来しているという信仰に由来していて、暑い最中の長い道程に必要だと考えて、タオルや履物が奉納されています。

17.極楽浜・宇曽利湖・震災の地蔵菩薩像
八角堂からさらに進むと、宇曾利湖に出ます。湖畔に広がる白砂の清浄な浜は、「極楽浜」と呼ばれます。
湖底からは硫黄ガスが噴き出ており、強酸性のため、特殊に適応したウグイ以外に生き物はいません。
7月の例大祭前後には、大量の風車、花束などが浜に林立し、菓子などが供えられます。これらは、亡くした家族のために参拝の方々が持参したもので、お供えが終わると、正面の山々に向って合掌し拝礼します。
これは、湖と正面の山々は恐山の西側にあり、その彼方には「極楽」があると信じられているからで、参拝者はその極楽にいるであろう、亡くなった家族などの幸福を祈るのです。このとき、多くの参拝者が故人の名前を呼びかけ、自らの参拝を告げて、死者を偲びます。

極楽浜には、東日本大震災の犠牲となられた方々を供養するための地蔵菩薩像が奉安されています。左右の鐘は、焼香の代わりに鳴らしていただいています。
像の背後のたくさんの手形は、参拝の方々がご自分の手に合うところに触れることで、震災の犠牲者を追悼していただきたく、山主が当時の多くの参拝者にご協力を願い、彫刻しました。現在は、東日本大震災のみならず、全国の災害犠牲者の追悼の場となっています。

18.五智山
極楽浜から続く参道の高台が五智如来の石像をお祀りする五智山です。五智如来は、大日如来の五つの智慧を体現しています。

19.龍神堂・稲荷堂
寺務所裏の階段上には、境内東側の丘の上に、護法龍天善神と稲荷明神が祀られています。竜神は雨ごいや止水、大漁祈願や海上安全など、農業や漁業に関わる神で、稲荷明神の信仰は、五穀豊穣や商売繁盛などを祈願するものです。ともに恐山の守護神です。